NAT.BREW(富山県)のはなし
醸造っておもしろい!
ワイン醸造家×木彫のまち「井波」のビール造り
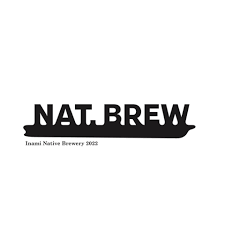
NAT.BREW
富山県南砺市
富山県西部に位置する南砺市井波地区。八乙女山の麓に広がるこの地は、室町時代に建立された瑞泉寺の門前町として栄え、今も町のあちこちでノミの音が響く「木彫り彫刻の町」として知られています。しっとりとした石畳の通りには、職人たちの工房や歴史的な建造物が軒を連ね、ものづくりの精神が深く息づいています。そんな職人の町に、新たな醸造所「NAT.BREW」が2022年12月にプレオープン、2023年2月からビールの提供を開始しました。ヘッドブルワーの望月俊祐さんにお話を聞きました。
「地酒に旅をさせるな」富山・井波に根ざすテロワール
僕がワインを造っていた頃、師匠からいつも言われていた言葉があります。

「地酒に旅をさせるな」。
その土地で人に愛されてこそ、本物の地酒なんだと。
その教えが、NAT.BREWが掲げる「土着醸造」の、まさに根っこにありますね。まずはこの南砺市で、井波という町で愛されるお酒を造りたい。その一心で、ブルワリーを始めた当初は、できたビールはほとんど地元でしか売らなかったんです。
もともと、30歳になったら醸造で独立すると決めていました。
だから、最初に就職した大手のワインメーカーも、ずっといるつもりはなかったんです。大きな組織だと、どうしても醸造工程の一部分しか担当させてもらえない。そこで、醸造の全てに携われる勝沼の老舗ワイナリーに転職。将来的な独立に向けて、キャリアを積むためのステップでした。
そこから富山に来たのは、妻が南砺市の出身だったのがきっかけです。
ずっと仕事ばかりで家族の時間を作ることができなかったし、子育て支援が充実している南砺市は子育て環境がすごく良いと聞いたので、思い切って(笑)。
どこに住んでいてもお酒は造れますしね。
ワイナリーの経験が活きた自由な酒造り

ただ、いざ富山に移住してみたらなかなか醸造の仕事が見つからなくて、しばらく「昆布」の営業をやっていたんです。お酒を造れても、売れなければ意味がない。だからまず、地元のものを売る営業を学ぼうと思って。
この昆布の営業が思いのほか面白くて!
富山の人の嗜好性や食習慣を知る絶好の機会になりました。富山の人はとにかく味覚が鋭敏で、家庭でもきちんと昆布やいりこで出汁をとる人が多いんです。日常的に本物の旨みに触れているから、そんな富山の人に受け入れられるお酒を造らなければ、と思いましたね。NAT.BREWの酒造りの考え方にも大きな影響を与えたと思います。
昆布って、同じ一枚でもカットする場所や方法、パッケージを変えるだけで、「出汁用」「昆布締め用」「昆布巻き用」と、用途や価値が変わるんです。日本「だし」文化は和食に限らず、さまざまなジャンルの料理で注目されているので、ワインの知識を活かして、フレンチやイタリアンのシェフにワインとの相性も考えて営業をしていました。
ひとつの素材を、どう解釈して、どう届けるか。
その経験が、今うちがやっているような、常識にとらわれない自由なビール造りに繋がっています。

やがてワイナリー立ち上げを手伝うことになり、日本酒の元杜氏とともにワイン醸造とワイナリーの立ち上げをしていたら、今度はビールのブルワリーを立ち上げるって話が舞い込んできて。井波の経営者が中心となって、地域主体のまちづくりに取り組む「ジソウラボ」という団体が、クラフトビールの起業家を募集していたんです。2019年、そこに僕は「ワインを造らせてくれ」って飛び込んだんだけど、経営パートナーの藤井公嗣さんは「いやビールを造ってくれ」って(笑)。
でも、醸造家としての経験を活かせて、自由な酒造りができるのは、ワインではなく「発泡酒免許」で手がけるビール造りだったんですよね。
発泡酒免許なら、規定量の麦芽を使えば、りんごでシードルを造っても、蜂蜜でミード(蜂蜜を主原料とする醸造酒)を造ってもいいわけです。まさに僕がやりたかったことでした。そこで、「ビールは8割、残りの2割は、僕が造りたい酒を造らせてほしい」と約束して、NAT.BREWが始まったんです。
木樽も造れる井波で、井波らしいビールをつくる
僕が今いるこの「井波」という町は、本当にユニークな場所です。
人口約8,000人の町に200人もの木彫り職人がいて、町を歩けば工房から木の香りが漂ってくる。その木彫り職人の多くが僕と同じように県外から来た人たち。だから、移住者や、何か新しいことを始めようとする人間に対してすごく寛容で、むしろおもしろがってくれる文化があるんですよ。

井波の木彫り文化も、NAT.BREWの土着醸造の軸になっていて、例えば定番の「HEY HEY HOO(ヘイヘイホー)」に使っている香木の「クロモジ」は、南砺の土地から生まれたもの。高級楊枝の原料としても使われるクロモジですが、林業の人にとっては雑木だそうで。僕にとっては宝物にもなる上品な香りをビールに閉じ込めています。
一方で、干し柿を使った「KUMA MASSIGURA(クママッシグラ)」にも、切実な物語があります。この辺りは干し柿が特産品なんですが、出荷制限によって販売できず、仕方なく木に放置される柿がたくさんあった。それがもったいないし、果物って収穫しないと次の年の生育サイクルが狂ってしまうんですよ。さらに、放置された柿はクマを人里に呼び寄せる原因にもなってしまう。そこで放置された干し柿を買い取ってビールに使ってみたんです。干し柿農家の方が喜んでくださったのがうれしかったですね。
こうして、地域の人たちのビールへの認識が少しずつ変わっていくのを感じます。
今では「お祭りにはNAT.BREWを」と言ってくれるまでになりました。手がけたビールが、人や町を繋いでいく。その中心にいるというのは不思議な感覚ですし、やりがいや生きがいになっていきます。

そして、井波はもうひとつ運命的な出会いをくれました。
NAT.BREWがある場所の目の前、斜め向かいに木樽工場があったんです!
木桶ではなく、日本では珍しい洋樽の製造所です。日本にわずか2軒しかない木樽工場ですよ?
もともとは地元のウイスキー蒸留所のために始まったそうですが、「井波の産業にしたい」という職人さんたちの思いから、独立した工場になったそうで。醸造所の目の前で、樽の修理も焼き直しも、さまざまな県産材を使うこともできる。
醸造家としてこんな奇跡は滅多にないでしょう。
これはもう「やれ」と言われているようなものです(笑)。
今後は木樽発酵と熟成、木樽を使ったビールにどんどん取り組みたい。
例えば、NAT.BREWでビールを熟成させた樽を日本酒の酒蔵さんに渡して、今度は日本酒の香りが移った樽がうちに戻ってくる。そんな樽の「履歴」が価値になるような取り組みも始まっています。

NAT.BREWで造りたいのは、ただおいしいだけの飲み物じゃない。
その一杯の背景にある物語や、井波という土地の空気、NAT.BREWの土着醸造を感じてもらえるような、一期一会のお酒を造りたいですね。
醸造の世界って、おもしろい!
取材・文/山口 紗佳
【公式HP】https://www.nat-brew.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/nat.brew_inami/
【facebook】https://www.facebook.com/NAT.BREW.INAMI

NAT.BREWのビールは一杯でもしっかり満足できるように、意識して造っています。なぜこの果物を使ったのか、なぜこの香りがするのか、背景にある物語に想いを馳せながら、ゆっくりと時間をかけて楽しんでいただけたら。そして、ビールを気に入ってくれたときは、この井波を訪れてみてください。
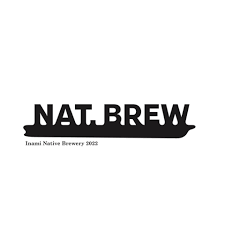
NAT.BREW
富山県南砺市
富山県西部に位置する南砺市井波地区。八乙女山の麓に広がるこの地は、室町時代に建立された瑞泉寺の門前町として栄え、今も町のあちこちでノミの音が響く「木彫り彫刻の町」として知られています。しっとりとした石畳の通りには、職人たちの工房や歴史的な建造物が軒を連ね、ものづくりの精神が深く息づいています。そんな職人の町に、新たな醸造所「NAT.BREW」が2022年12月にプレオープン、2023年2月からビールの提供を開始しました。ヘッドブルワーの望月俊祐さんにお話を聞きました。
「地酒に旅をさせるな」富山・井波に根ざすテロワール
僕がワインを造っていた頃、師匠からいつも言われていた言葉があります。

「地酒に旅をさせるな」。
その土地で人に愛されてこそ、本物の地酒なんだと。
その教えが、NAT.BREWが掲げる「土着醸造」の、まさに根っこにありますね。まずはこの南砺市で、井波という町で愛されるお酒を造りたい。その一心で、ブルワリーを始めた当初は、できたビールはほとんど地元でしか売らなかったんです。
もともと、30歳になったら醸造で独立すると決めていました。
だから、最初に就職した大手のワインメーカーも、ずっといるつもりはなかったんです。大きな組織だと、どうしても醸造工程の一部分しか担当させてもらえない。そこで、醸造の全てに携われる勝沼の老舗ワイナリーに転職。将来的な独立に向けて、キャリアを積むためのステップでした。
そこから富山に来たのは、妻が南砺市の出身だったのがきっかけです。
ずっと仕事ばかりで家族の時間を作ることができなかったし、子育て支援が充実している南砺市は子育て環境がすごく良いと聞いたので、思い切って(笑)。
どこに住んでいてもお酒は造れますしね。
ワイナリーの経験が活きた自由な酒造り

ただ、いざ富山に移住してみたらなかなか醸造の仕事が見つからなくて、しばらく「昆布」の営業をやっていたんです。お酒を造れても、売れなければ意味がない。だからまず、地元のものを売る営業を学ぼうと思って。
この昆布の営業が思いのほか面白くて!
富山の人の嗜好性や食習慣を知る絶好の機会になりました。富山の人はとにかく味覚が鋭敏で、家庭でもきちんと昆布やいりこで出汁をとる人が多いんです。日常的に本物の旨みに触れているから、そんな富山の人に受け入れられるお酒を造らなければ、と思いましたね。NAT.BREWの酒造りの考え方にも大きな影響を与えたと思います。
昆布って、同じ一枚でもカットする場所や方法、パッケージを変えるだけで、「出汁用」「昆布締め用」「昆布巻き用」と、用途や価値が変わるんです。日本「だし」文化は和食に限らず、さまざまなジャンルの料理で注目されているので、ワインの知識を活かして、フレンチやイタリアンのシェフにワインとの相性も考えて営業をしていました。
ひとつの素材を、どう解釈して、どう届けるか。
その経験が、今うちがやっているような、常識にとらわれない自由なビール造りに繋がっています。

やがてワイナリー立ち上げを手伝うことになり、日本酒の元杜氏とともにワイン醸造とワイナリーの立ち上げをしていたら、今度はビールのブルワリーを立ち上げるって話が舞い込んできて。井波の経営者が中心となって、地域主体のまちづくりに取り組む「ジソウラボ」という団体が、クラフトビールの起業家を募集していたんです。2019年、そこに僕は「ワインを造らせてくれ」って飛び込んだんだけど、経営パートナーの藤井公嗣さんは「いやビールを造ってくれ」って(笑)。
でも、醸造家としての経験を活かせて、自由な酒造りができるのは、ワインではなく「発泡酒免許」で手がけるビール造りだったんですよね。
発泡酒免許なら、規定量の麦芽を使えば、りんごでシードルを造っても、蜂蜜でミード(蜂蜜を主原料とする醸造酒)を造ってもいいわけです。まさに僕がやりたかったことでした。そこで、「ビールは8割、残りの2割は、僕が造りたい酒を造らせてほしい」と約束して、NAT.BREWが始まったんです。
木樽も造れる井波で、井波らしいビールをつくる
僕が今いるこの「井波」という町は、本当にユニークな場所です。
人口約8,000人の町に200人もの木彫り職人がいて、町を歩けば工房から木の香りが漂ってくる。その木彫り職人の多くが僕と同じように県外から来た人たち。だから、移住者や、何か新しいことを始めようとする人間に対してすごく寛容で、むしろおもしろがってくれる文化があるんですよ。

井波の木彫り文化も、NAT.BREWの土着醸造の軸になっていて、例えば定番の「HEY HEY HOO(ヘイヘイホー)」に使っている香木の「クロモジ」は、南砺の土地から生まれたもの。高級楊枝の原料としても使われるクロモジですが、林業の人にとっては雑木だそうで。僕にとっては宝物にもなる上品な香りをビールに閉じ込めています。
一方で、干し柿を使った「KUMA MASSIGURA(クママッシグラ)」にも、切実な物語があります。この辺りは干し柿が特産品なんですが、出荷制限によって販売できず、仕方なく木に放置される柿がたくさんあった。それがもったいないし、果物って収穫しないと次の年の生育サイクルが狂ってしまうんですよ。さらに、放置された柿はクマを人里に呼び寄せる原因にもなってしまう。そこで放置された干し柿を買い取ってビールに使ってみたんです。干し柿農家の方が喜んでくださったのがうれしかったですね。
こうして、地域の人たちのビールへの認識が少しずつ変わっていくのを感じます。
今では「お祭りにはNAT.BREWを」と言ってくれるまでになりました。手がけたビールが、人や町を繋いでいく。その中心にいるというのは不思議な感覚ですし、やりがいや生きがいになっていきます。

そして、井波はもうひとつ運命的な出会いをくれました。
NAT.BREWがある場所の目の前、斜め向かいに木樽工場があったんです!
木桶ではなく、日本では珍しい洋樽の製造所です。日本にわずか2軒しかない木樽工場ですよ?
もともとは地元のウイスキー蒸留所のために始まったそうですが、「井波の産業にしたい」という職人さんたちの思いから、独立した工場になったそうで。醸造所の目の前で、樽の修理も焼き直しも、さまざまな県産材を使うこともできる。
醸造家としてこんな奇跡は滅多にないでしょう。
これはもう「やれ」と言われているようなものです(笑)。
今後は木樽発酵と熟成、木樽を使ったビールにどんどん取り組みたい。
例えば、NAT.BREWでビールを熟成させた樽を日本酒の酒蔵さんに渡して、今度は日本酒の香りが移った樽がうちに戻ってくる。そんな樽の「履歴」が価値になるような取り組みも始まっています。

NAT.BREWで造りたいのは、ただおいしいだけの飲み物じゃない。
その一杯の背景にある物語や、井波という土地の空気、NAT.BREWの土着醸造を感じてもらえるような、一期一会のお酒を造りたいですね。
醸造の世界って、おもしろい!
取材・文/山口 紗佳
【公式HP】https://www.nat-brew.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/nat.brew_inami/
【facebook】https://www.facebook.com/NAT.BREW.INAMI

NAT.BREWのビールは一杯でもしっかり満足できるように、意識して造っています。なぜこの果物を使ったのか、なぜこの香りがするのか、背景にある物語に想いを馳せながら、ゆっくりと時間をかけて楽しんでいただけたら。そして、ビールを気に入ってくれたときは、この井波を訪れてみてください。

OTHER BREWERIES
その他のブルワリー


















